
阪大D3センター、オープンサイエンス向けコンピューティング・データプラットフォーム試験運用
大阪大学D3センターは、オープンサイエンスを推進するために設計された、新たなデータ・コンピューティングプラットフォームの試験運用を開始しました。
「Osaka university Compute and sTOrage Platform Urging open Science(OCTOPUS)」と名付けられたこの試験運用は今月開始され、12月から本格運用が開始される予定です。
OCTOPUSは日本電気(NEC)が開発しました。理論上の計算性能は2.293ペタフロップスで、「NEC LX201Ein-1」約140台の計算ノードで構成されます。各ノードには第6世代インテルXeon Scalableプロセッサ2基と大容量ストレージが搭載されており、NECによれば、D3センターの従来システム比で約1.5倍の性能を提供するとのことです。
本システムはデータ生成を含むプロセスを自動記録・管理するプロバンス管理機能を備えており、研究データの共有を促す「オープンサイエンス」に貢献していくことが期待されます。プロバンス機能は2025年12月より稼働予定です。
NECによれば、学術研究ではスーパーコンピュータを用いた膨大なデータの日常的な分析・生成が増加しており、従来、これには手動での記録が必要でした。
この課題を解決するため、D3センターとNECが設立した共同研究機関「高性能計算・データ分析融合研究基盤協働研究所」の伊達所長率いる研究グループは、クラスター型スーパーコンピュータにおける計算プロバンスを追跡・記録・管理・可視化する「SCUP-HPC(Scientific Computing Unifying Provenance – High Performance Computing)」を開発しました。
大阪大学D3センターとNECは発表のなかで、「従来のスーパーコンピュータ応用分野に加え、産業応用やAI・ビッグデータ活用の基盤として次世代高性能サーバーの導入・活用を推進し、先端技術開発に貢献すること」を継続的に推進すると表明しました。
大阪大学D3センターは、同センターのウェブサイトによると、「学術研究・教育を伴う計算・情報処理を科学者・研究者が行える国家共同利用施設として、大規模計算システムを提供する」ことを掲げており、MDX IIクラスター、SQUIDクラスター、ONIONアグリゲーションプラットフォームも運用しています。
この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




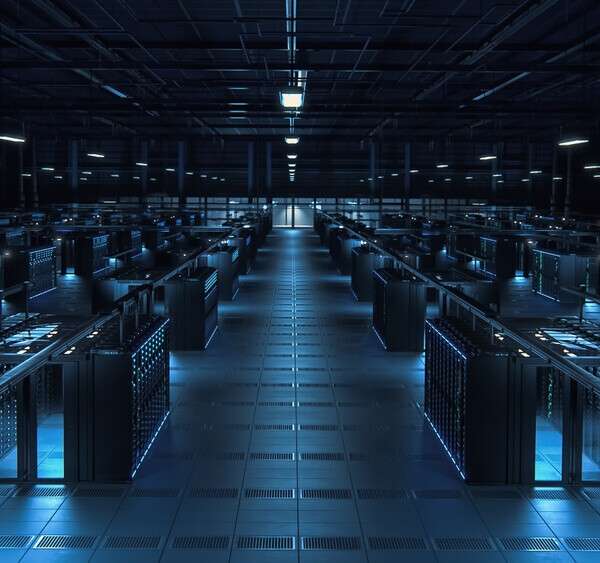

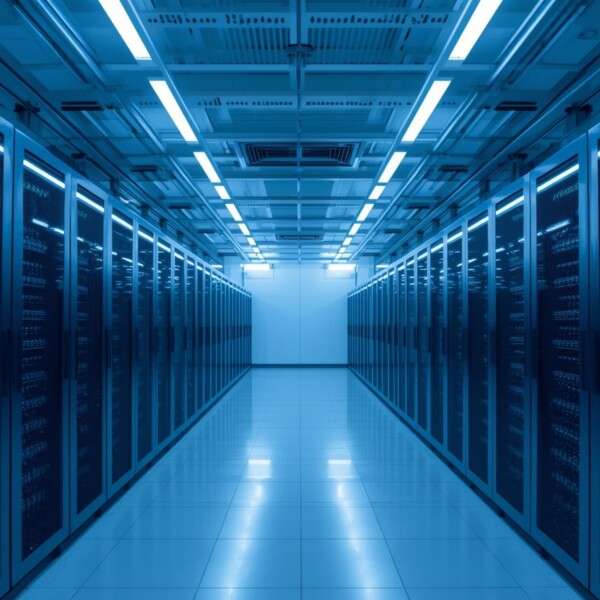



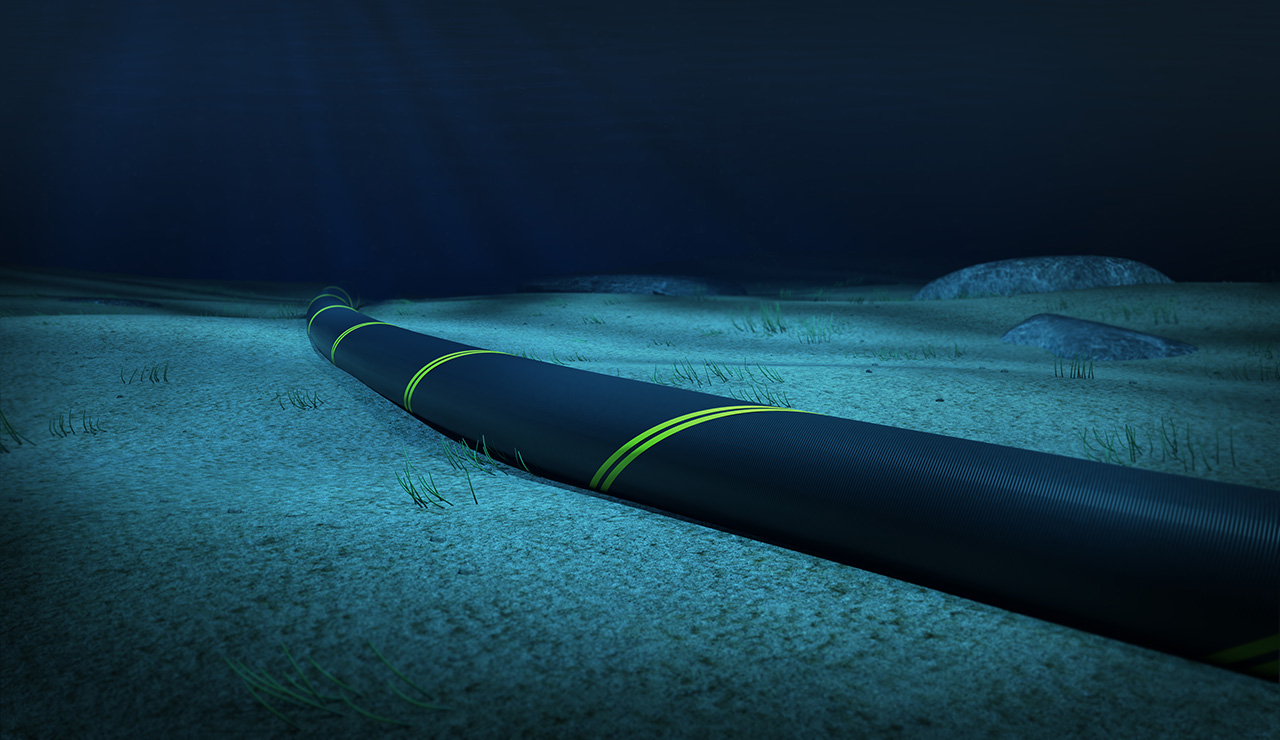
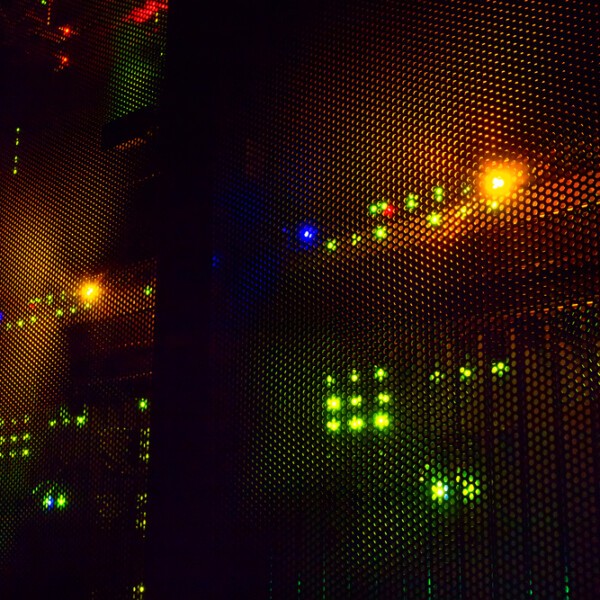




















この記事へのコメントはありません。