
富士通が1万量子ビットを超える量子コンピュータの開発を開始
富士通は、計画中の1万量子ビットを超える超伝導型量子コンピュータの研究開発を開始しました。システムの構築は、2030年までに完了する予定です。
この量子コンピュータは当初、250の論理量子ビットで動作し、富士通が開発した早期段階のFault-Tolerant Quantum Computer(early-FTQC)アーキテクチャである、「STARアーキテクチャ」を採用します。
システムの完成後は、「超伝導型とダイヤモンドスピンベースの量子ビットの統合を目標とした先進的な研究プロジェクト」を推進し、2035年までに1,000論理量子ビットマシンを実現するほか、複数の相互接続された量子ビットチップの可能性に関する研究を進める予定です。
このプロジェクトは、NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)が実施パートナーとして選定した「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」の一環として実施されます。
2027年まで継続される見込みで、日本の国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST)と国立研究開発法人理化学研究所(理研)が支援します。富士通は、研究の重点を、高スループット・高精度量子ビット製造技術、チップ間インターコネクト技術、高密度実装と低コスト量子ビット制御技術、および量子エラー訂正向けデコーディング技術に置くとしています。
富士通株式会社 執行役員副社長 CTO、システムプラットフォーム担当であるVivek Mahajanは、次のように述べました。「当社は、ソフトウェアからハードウェアまで幅広い分野で量子コンピュータの分野における世界的なリーダーとして既に認識されています。このプロジェクトは、NEDOが主導するもので、当社の『Made in Japanのフォールトトレラント超伝導量子コンピュータのさらなる開発』という目標に大きく貢献するでしょう。」
さらに、「当社のロードマップの一環として、超伝導量子コンピューティングとダイヤモンドスピン技術を組み合わせることも目指しています。2030年度に250論理量子ビット、2035年度に1,000論理量子ビットを実現することで、実用的量子計算分野において世界的に先導的な役割を果たすことを誓っています」と付け加えました。
2025年4月、富士通と理研は、256量子ビットの超伝導量子コンピューターの開発を発表しました。これは、両者が2023年10月に理研RQC-富士通連携センターで共同開発・導入した64量子ビットの量子コンピューターを基盤としたものです。
この256量子ビットのマシンは、64量子ビットの前世代機で確立された同じユニットセル設計を採用しており、システム密度が4倍に増加したにもかかわらず、従来開発された希釈冷凍機内でスケーリング可能です。両者は、この256量子ビット超伝導量子コンピュータを、共同で開発しているハイブリッド量子コンピューティングプラットフォームに統合する計画です。
この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに一部を抄訳したものです。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




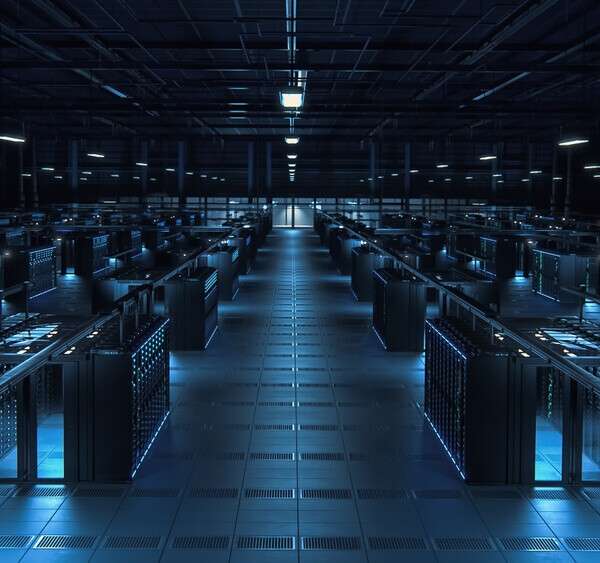

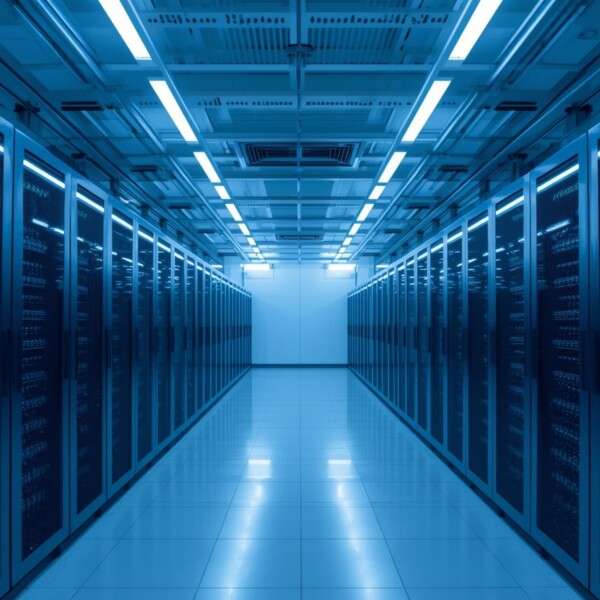



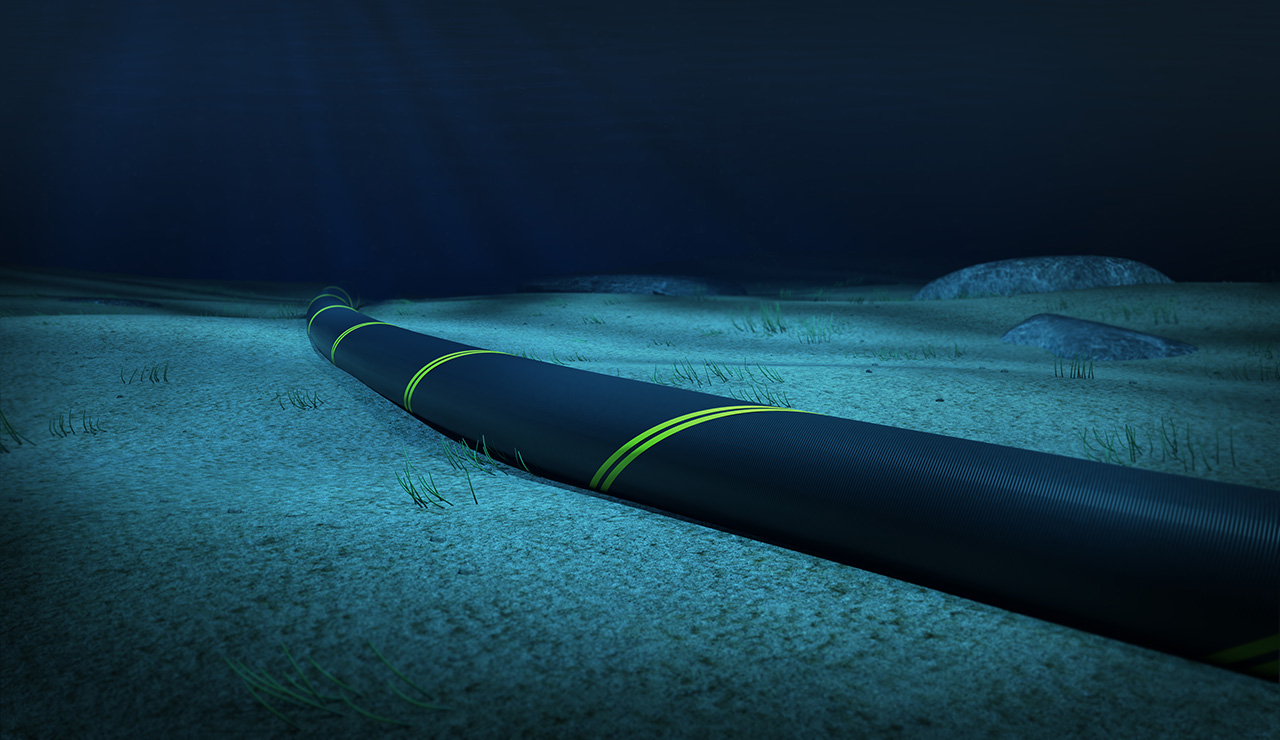
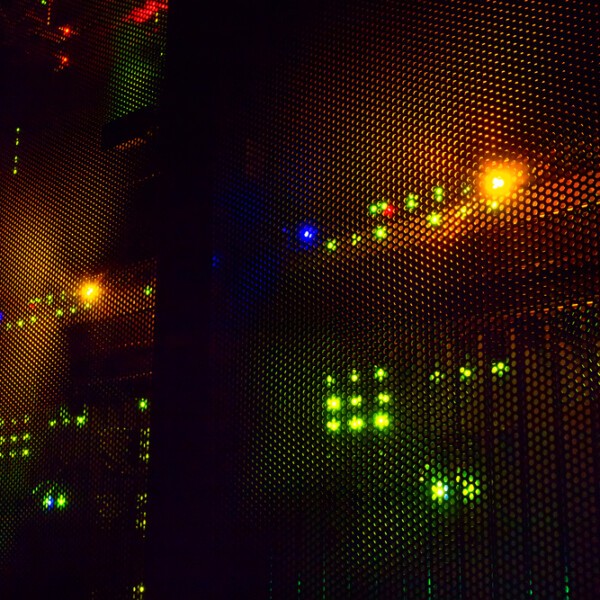






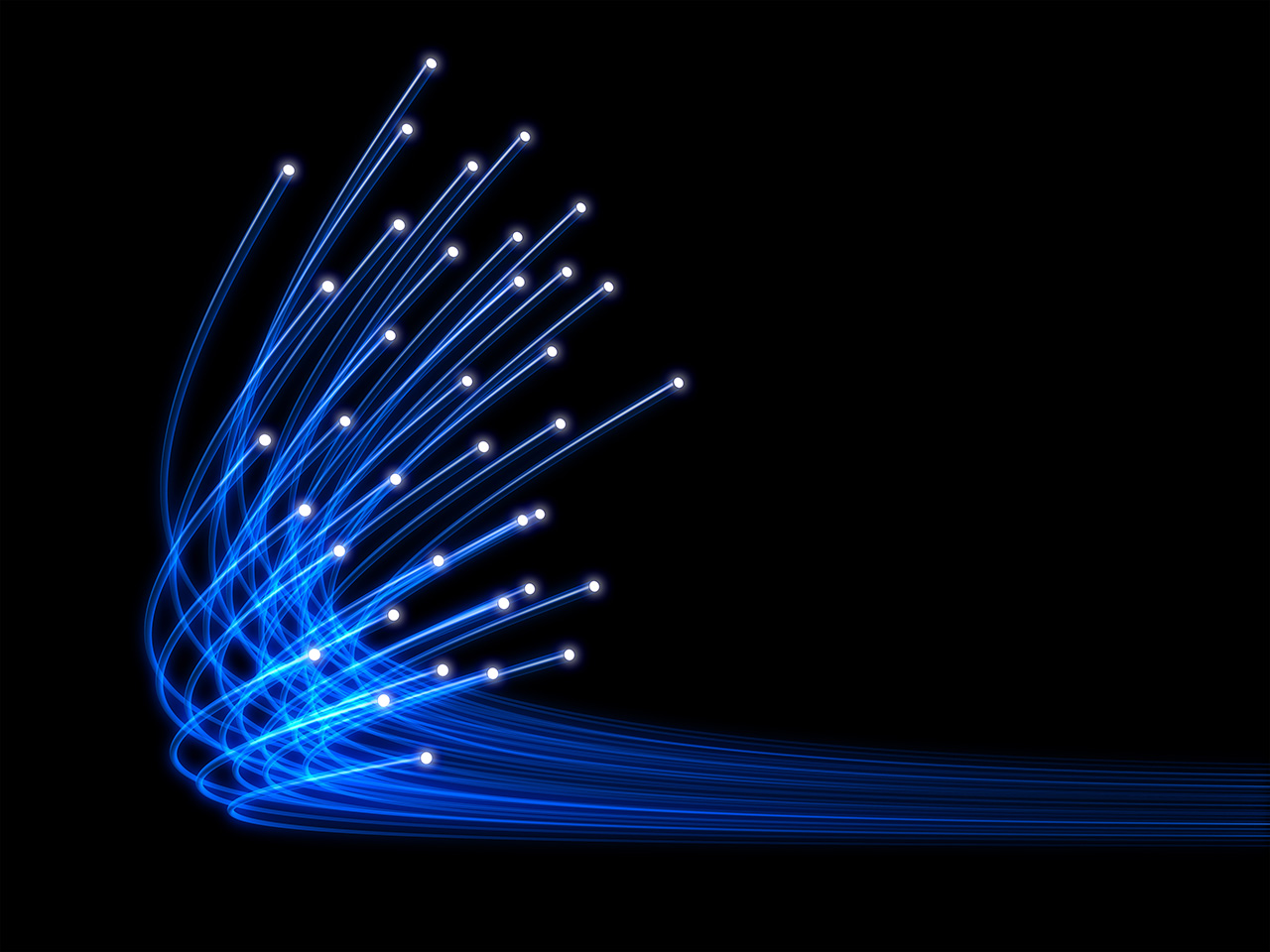












この記事へのコメントはありません。