
東大がIBM量子コンピュータを156量子ビットHeron QPUでアップグレードへ
東京大学、量子コンピュータを「Miyabi」スーパーコンピュータと今年後半に連携予定
IBMは、156量子ビットのIBM Heron量子プロセッシングユニット(QPU)を導入し、国立大学法人東京大学(以下、東京大学)のQuantum System Oneをアップグレードすると発表しました。
これは、2021年に東京大学のシステムが初めて設置されて以来、2度目の更新となります。当初は27量子ビットのIBM Falcon QPUが導入されていましたが、2023年に127量子ビットのIBM Eagle QPUにアップグレードされました。
2023年12月に初めて発表されたIBMのQuantum Heronプロセッサーは、Eagle QPUと比較して2量子ビットのエラー率が3~4倍改善され、133個の固定周波数量子ビットを達成することができました。しかし、2025年4月、IBMは同社のHeron r2プロセッサーが提供する156量子ビットを提供する、「Aachen」と名付けられた新しい量子システムを発表しています。
Quantum System Oneのアップグレードに加え、東京大学は今年後半、量子コンピュータをスーパーコンピュータ「Miyabi」と連携させ、量子イノベーションイニシアティブ協議会(QII)コンソーシアムの産学メンバーに新たな計算能力へのアクセスを提供する計画です。
「Miyabi」は、東京大学と筑波大学が先端ハイパフォーマンスコンピューティング共同研究センター(JCAHPC)を通じて共同運用しているスーパーコンピュータです。
東京大学の相原 博昭理事・副学長は、「今回のIBM Heron量子プロセッサーへの更新により、Miyabiのスーパーコンピューターと連携し、量子力学とAIの能力を活用したユースケースの開発がさらに進み、科学における計算可能な問題の領域が拡大し、社会的課題の解決に向けた取り組みが加速されます」と述べています。
また、IBM QuantumのVPであるJay Gambettaは、次のように述べました。「当社の最新かつ最高性能のIBM Heron QPUをUTokyo’s IBM Quantum System Oneに搭載し、同システムをMiyabiスーパーコンピュータに接続することで、東京大学はスーパーコンピューティングの未来を定義する世界有数の組織に加わることになります。この量子中心スパコンは、QIIコンソーシアムのメンバーに対し、量子的な優位性が得られると予想される問題を解決するための、より強力な新たな計算能力を提供することになります。」
東京大学のIBM Quantum System Oneは、2019年にシステムが初めて発売されて以来、IBMが顧客に出荷した5台のオンプレミス量子コンピューターのうちの1台です。
IBMは2025年初頭の時点で、13台の実用規模の量子コンピューター(100量子ビットを超えるシステムを含む)をニューヨーク州ポキプシー、ドイツのデータセンター、および世界中の顧客拠点で稼働させています。
同社が引用した公開データによると、2016年以降、合計で80台弱の量子システムを配備しており、これは世界の他の国々の合計よりも多いとのことです。
2025年2月の報告によると、IBMは2017年第1四半期に量子ユニットを発足して以来、2024年第4四半期までの間に、ほぼ10億ドルの成約を達成したとのことです。
この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




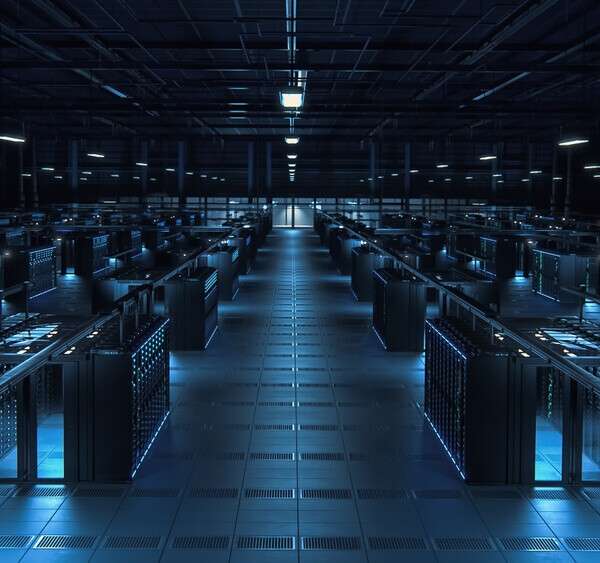

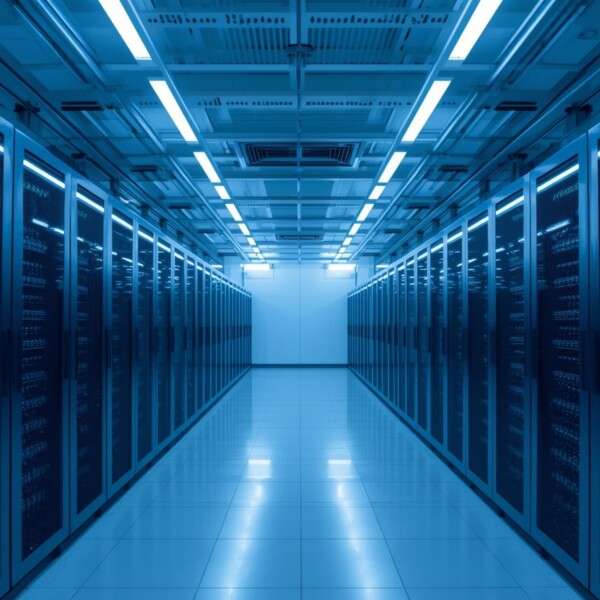



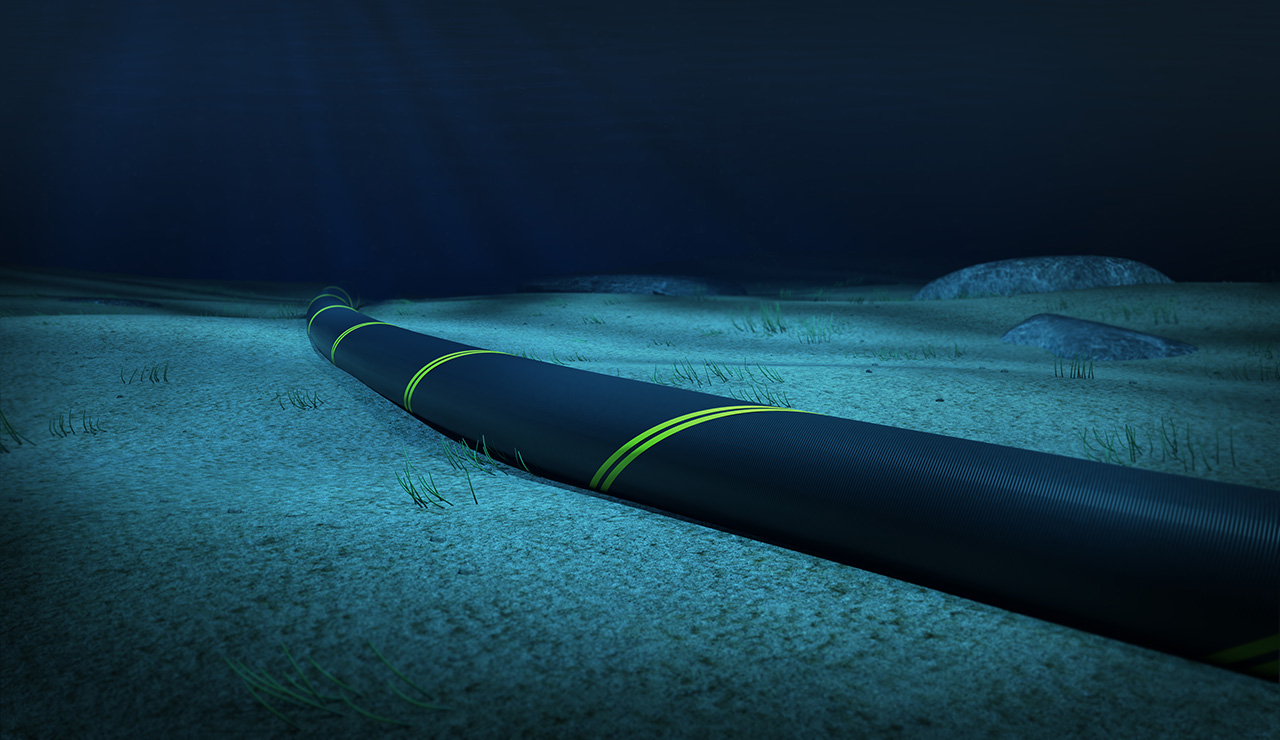
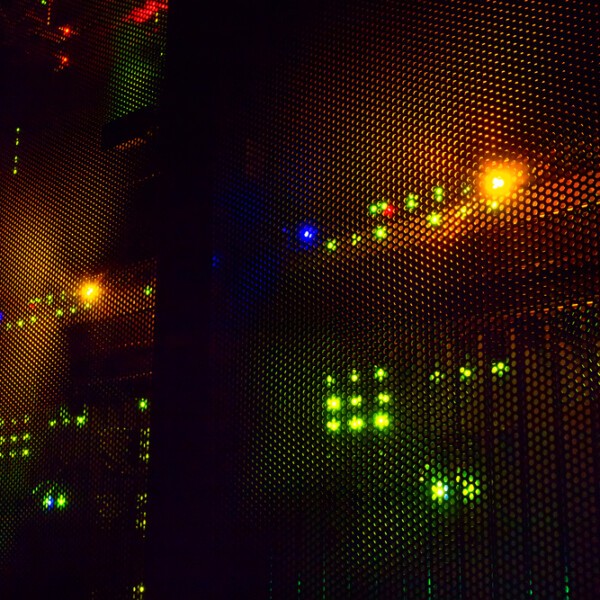




















この記事へのコメントはありません。