
IBM、分散型量子ネットワーク開発でシスコと提携
2030年までのPOC提供を目指す
IBMはシスコと協力し、2030年代初頭までにネットワーク化された分散型量子コンピューティングの基盤開発を進めています。
ネットワークの初期実証は今後5年以内に提供される見込みで、IBMは本プロジェクトが量子コンピューティング、センサー、通信の将来的な支援に加え、量子インターネットの基盤構築に寄与すると述べています。
今月初め、IBMは2026年末までに量子優位性を達成し、2029年までにフォールト・トレラント(耐障害性)量子コンピュータの開発目標を達成する見通しであると発表しました。
このPOC(概念実証)が成功すれば、個々の大規模なフォールト・トレラント量子コンピュータを連携させ、数万から数十万の量子ビットにわたる計算を実行できるネットワークの実証となります。初期実証では、異なる極低温環境下にある複数の量子コンピュータから量子ビットをエンタングル(entangle)させる予定です。
ただしこれを実現するには、マイクロ波-光変換器や支援ソフトウェアスタックを含む新たな接続技術をIBMとシスコが開発する必要があります。さらにネットワークを2台以上の量子コンピュータに拡張するには、建物間やデータセンター間など長距離での量子ビット伝送手法の探求が求められます。
IBMは量子処理ユニット(QPU)のインターフェースとなる量子ネットワークユニット(QNU)を開発します。QNUはQPU内の静止状態の量子情報を取り込み、QNUを介して「飛行」量子情報に変換し、ネットワークを通じて複数の量子コンピュータ間でさらに連結するとIBMは声明で述べています。
両社はさらに、新規ハードウェアとオープンソースソフトウェアで構成されるネットワークブリッジが、シスコの量子ネットワークノードを活用し、QNUインターフェースを介してデータセンター内の多数のIBM QPUを接続する方法についても調査する計画を立てており、このアプローチは将来的に複数のデータセンターにまたがるQPUの接続にも拡張できる可能性があります。これにより、より大規模な量子ネットワークがさらに長距離にわたり拡張され、将来の量子コンピューティングインターネットの基盤が形成されることになります。
 「IBMのロードマップには、今世紀末までに大規模かつ耐障害性のある量子コンピューターを提供するという計画が含まれている」と、IBMフェロー兼IBMリサーチ所長のJay Gambettaは述べています。「シスコと協力し、このような複数の量子コンピューターを分散型ネットワークに接続する方法を探求することで、量子コンピューティングの計算能力をさらに拡張する方法を追求していきます。そしてコンピューティングの未来を構築する中で、我々のビジョンは、より大規模な高性能コンピューティングアーキテクチャ内における量子コンピュータの可能性の限界を押し広げていくでしょう」
「IBMのロードマップには、今世紀末までに大規模かつ耐障害性のある量子コンピューターを提供するという計画が含まれている」と、IBMフェロー兼IBMリサーチ所長のJay Gambettaは述べています。「シスコと協力し、このような複数の量子コンピューターを分散型ネットワークに接続する方法を探求することで、量子コンピューティングの計算能力をさらに拡張する方法を追求していきます。そしてコンピューティングの未来を構築する中で、我々のビジョンは、より大規模な高性能コンピューティングアーキテクチャ内における量子コンピュータの可能性の限界を押し広げていくでしょう」
シスコ傘下Outshiftのゼネラルマネージャー兼シニアバイスプレジデント、Vijoy Pandeyは次のように付け加えています。「量子コンピューティングを有用な規模に拡大するには、単なる個々の大型マシン構築だけでなく、それらを相互接続することが不可欠です。IBMはスケールアップに向けた積極的なロードマップで量子コンピュータを開発しており、我々はスケールアウトを可能にする量子ネットワークを提供します。 我々は、量子コンピュータを接続するハードウェア、それらを横断して計算を実行するソフトウェア、そしてそれらを機能させるネットワークインテリジェンスを含む、完全なシステム課題としてこれを解決しています。」
この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




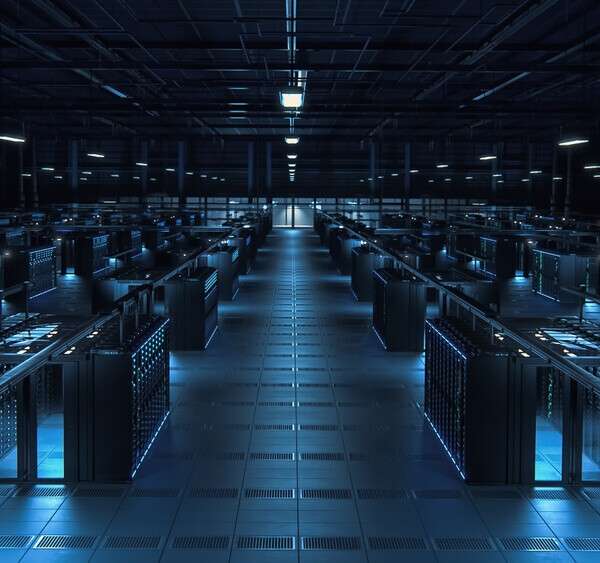

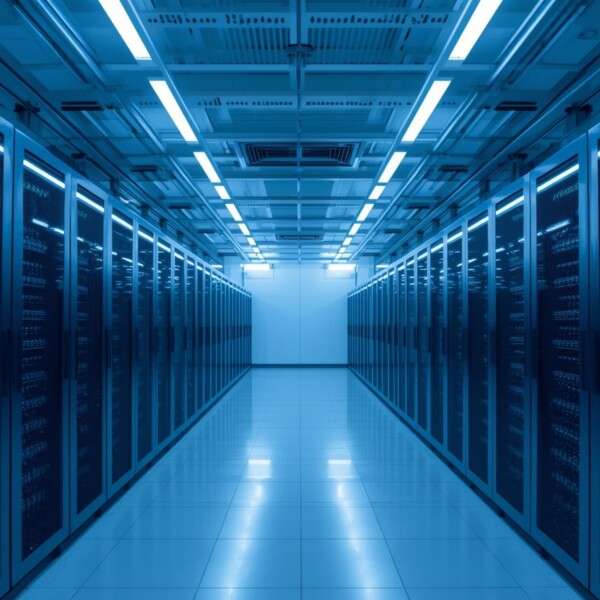



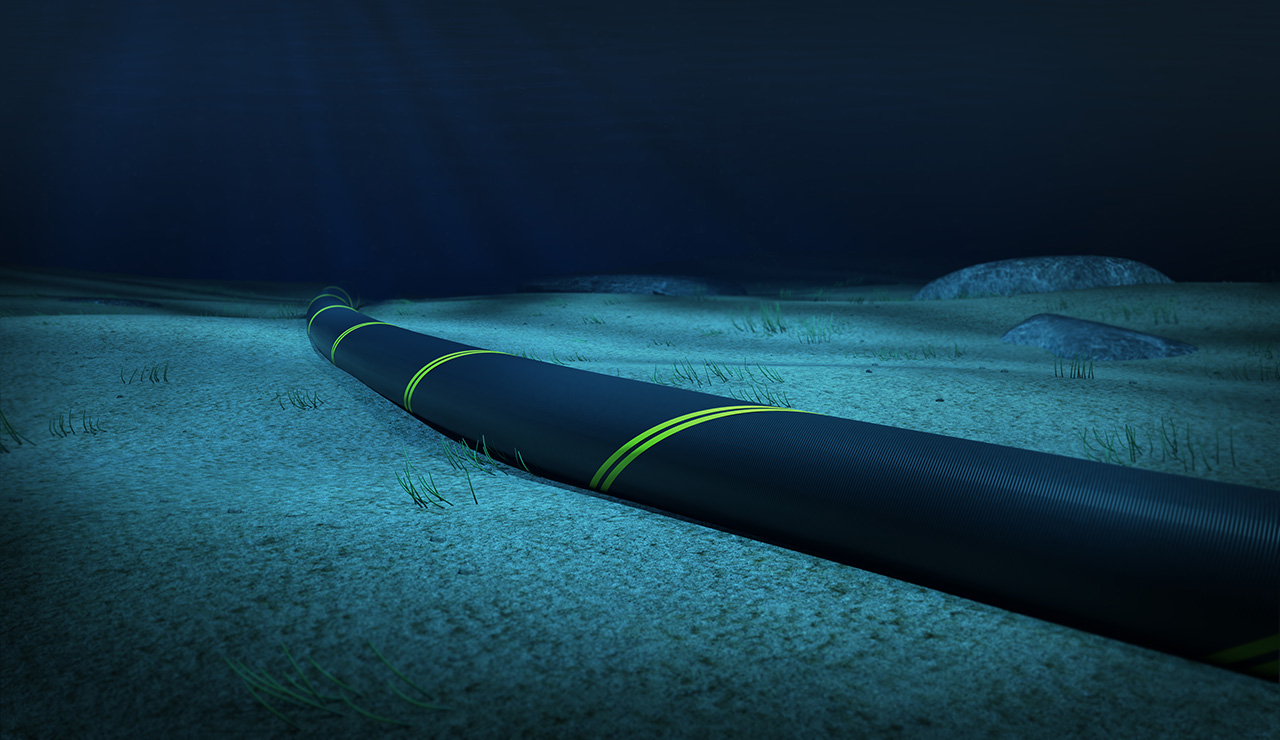
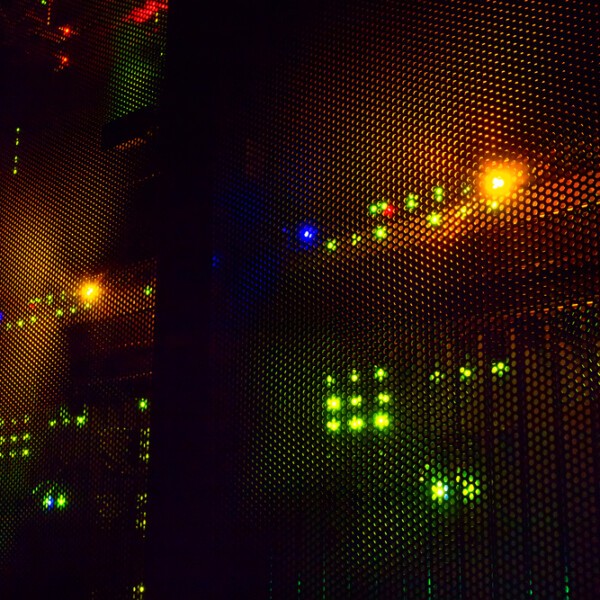







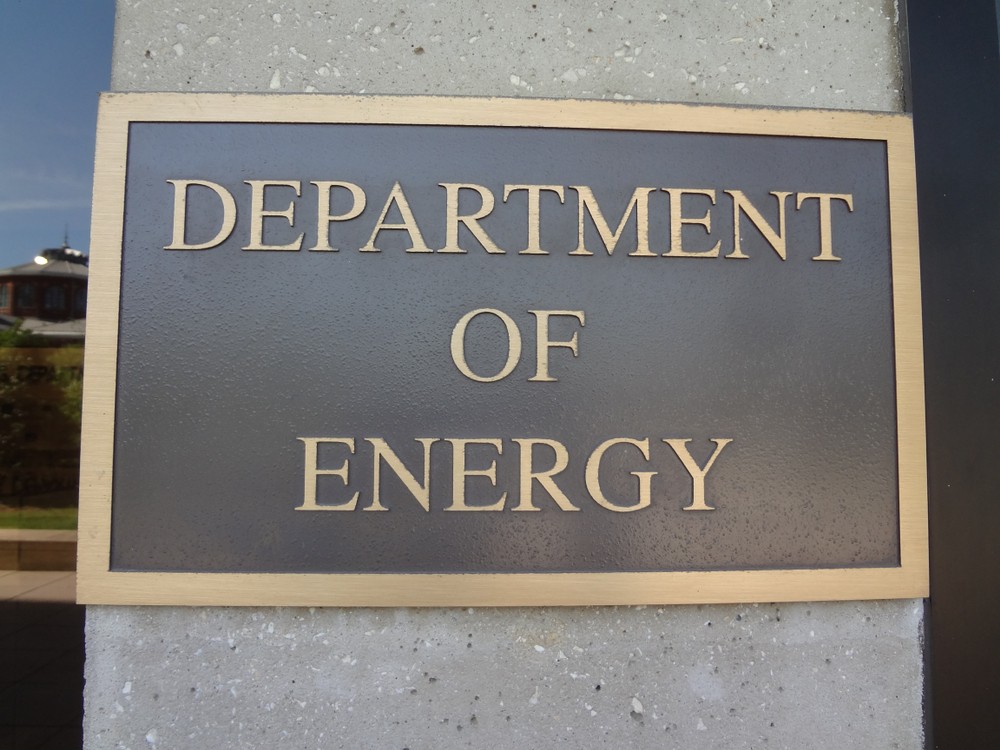





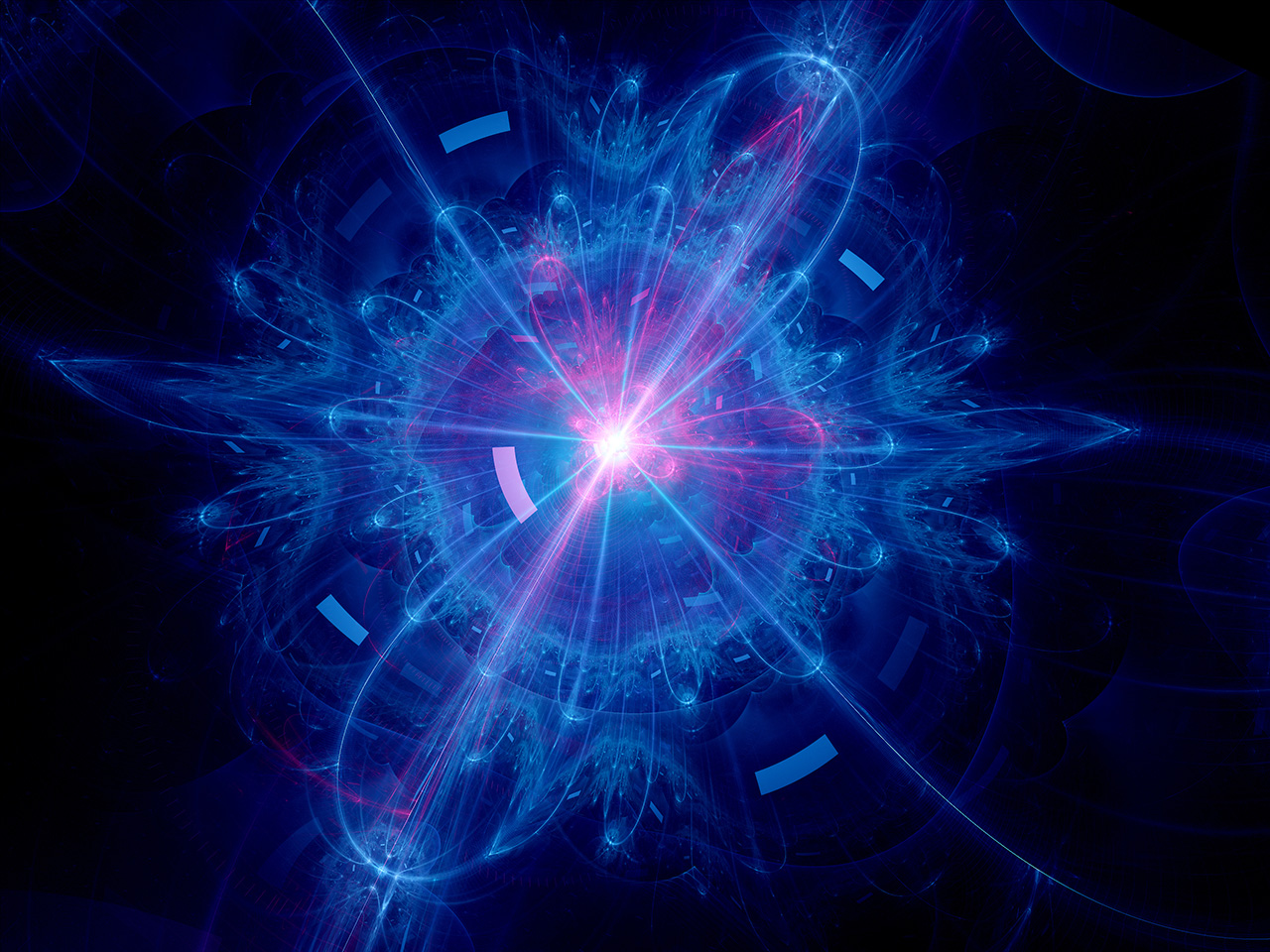

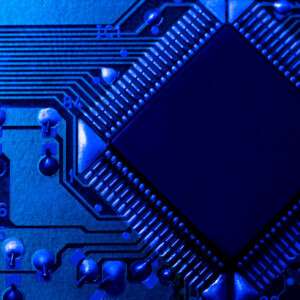


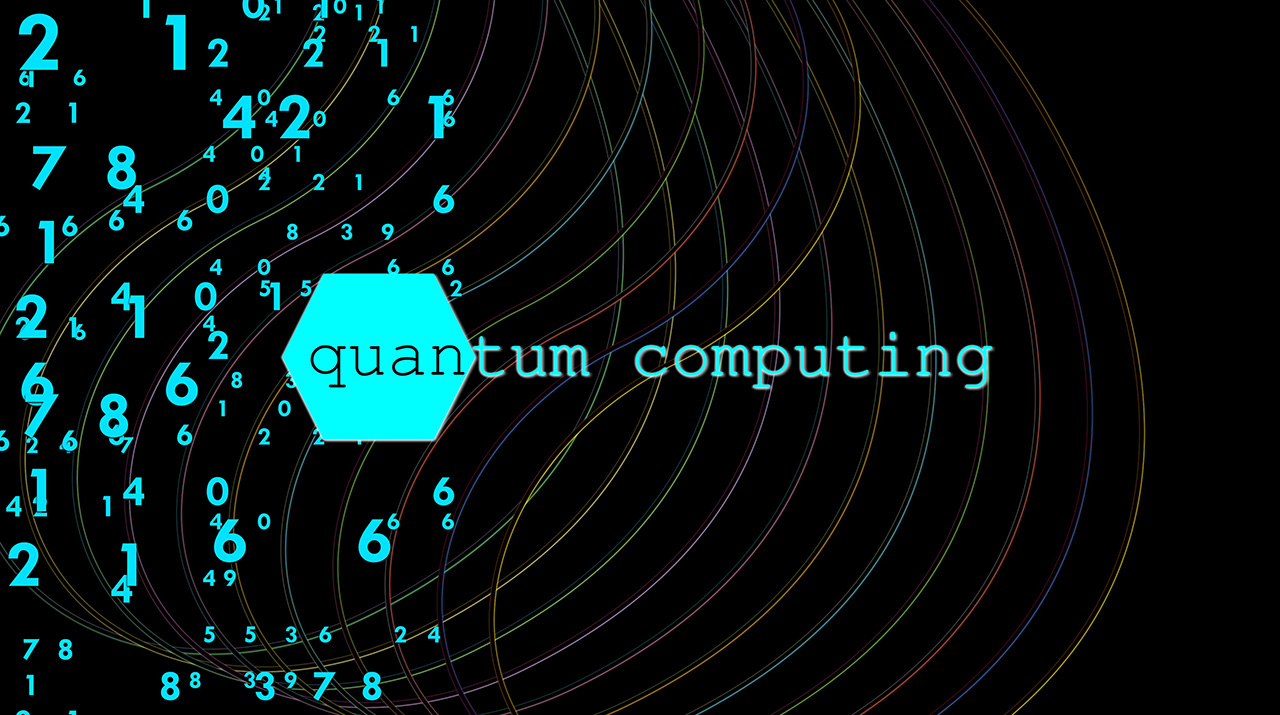
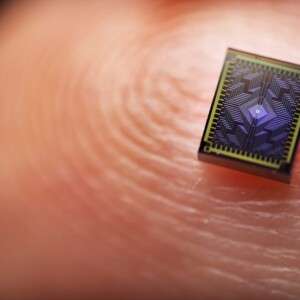
この記事へのコメントはありません。