
「誰も自宅の裏手にデータセンターを望んでいるわけではない」とマイクロソフトの弁護士は語る
ハイパースケーラーの弁護士も、地方の反対派に同意
マイクロソフトの弁護士が「誰も自宅の裏手にデータセンターを望んでいるわけではない」とコメントしました。
この発言をしたのは、マイクロソフトの企業法務顧問であるLyndi Stoneです。彼女は、法律事務所Norton Rose Fulbrightが主催したウェビナー「Data centers: Construction, contracts and debt.(データセンター:建設、契約、債務)」に登壇した際に、この発言を行いました。
同氏は「データセンターは従来、コミュニティや住宅地、都市部から離れた場所に建設されてきましたが、こうした地域に進出するにつれ近隣住民が身近になる、ただ誰も自宅の裏手のデータセンターを望んではいない」と指摘しました。
「私自身も自宅の裏手にデータセンターは欲しくない」
現在、米国および世界中でデータセンター建設の積極的な拡大を推進しているマイクロソフトの代理人を務める同氏のこの発言は、多くの場合マイクロソフトの資金提供と支援を受けているデータセンター計画に対して、多くの地方コミュニティが表明している懸念を直接反映しています。
こうした懸念は主に以下の点に集約されるています。光熱費の上昇、環境や地域の景観への影響、さらに秘密保持契約(NDA)の締結や計画審査手続きの迅速化に関する手続き上の問題です。その結果、提案は完全に拒否されたり、撤回されることがあります。
マイクロソフトもこうした挫折を数多く経験してきました。つい数週間前にも、ウィスコンシン州カレドニアでのデータセンター申請を、地域住民の反対を受けて撤回する決断を下しました。
サティア・ナデラCEOは、2026会計年度までにAI処理能力を80%以上増強し、今後2年間でデータセンターの設置面積を「ほぼ倍増」させる計画だと述べています。同社はまた、2025年だけで約2GWのデータセンターを立ち上げたとし、直近四半期では設備投資が前期比50%増の349億ドルに急増し、そのうち約111億ドルがデータセンター賃貸料に充てられたと説明しました。
Lyndi Stoneは雇用に関する懸念にも触れ、「データセンターは、稼働開始後もそれほど多くの雇用を生み出すわけではありません。建設段階では一時的に雇用が生まれますが、実際にデータセンターが地元に立地しても、地域社会に大きな恩恵をもたらすわけではないのです」と述べました。
データセンター開発事業者は、施設が生み出す雇用の数を強調することが多いですが、地元住民からは「多くの仕事は一時的で、専門性が高く、地元ではなく外部の業者が担うことが多いのではないか」との懸念が寄せられています。
これに対し、Norton Rose Fulbrightの顧問弁護士であるShelley Eichenlaubは、これはオーナーが直面する問題であり、「グローバルなサプライチェーンの制約は、地域の支援によってある程度解消できる可能性がある」と述べました。
「高度に専門化された設備、例えば変圧器などは街中で買えるものではありませんし、そうした問題を解決することもできません。しかし、データセンター建設に関する基礎工事や、一般的な建設作業部分については、地元の業者を活用することも可能です」と語りました。
Lyndi Stoneはまた、こうした地域でのデータセンター建設の課題について言及し、「地域住民によって選出された政府関係者は、当然ながら有権者を満足させたいと考えています。企業側も、許可を得て事業を継続するためには、住民を満足させる必要があります」と述べました。
AIの急速な普及に伴い、こうした反対運動は特に広がりを見せています。迅速な電力供給を求めるデータセンター事業者は、従来の大都市から、より小規模な地方コミュニティへと進出する傾向を強めています。こうした地域では、データセンター市場がまだ発展途上であることを示す事例も多く見られます。たとえば、多くの自治体では、そもそも「データセンター」という土地利用の分類が都市計画の規定に含まれておらず、建設計画を審査する前に、その用途を新たに追加する必要があります。
この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




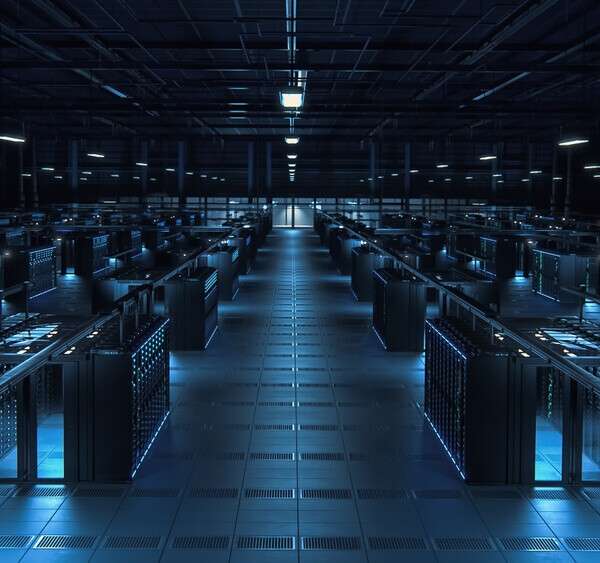

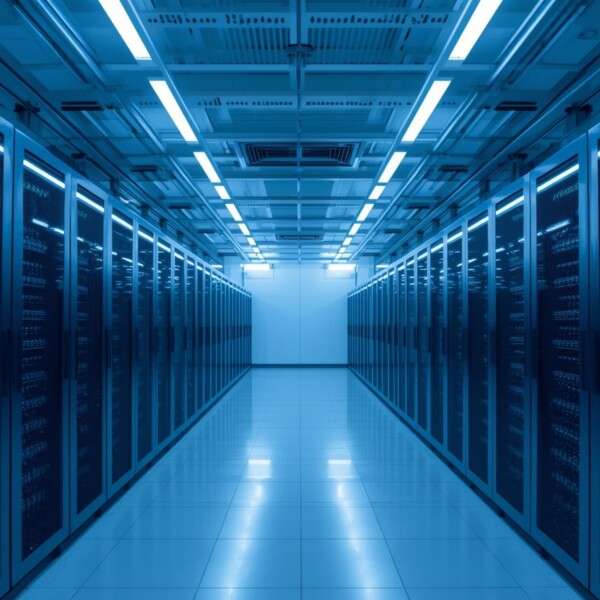



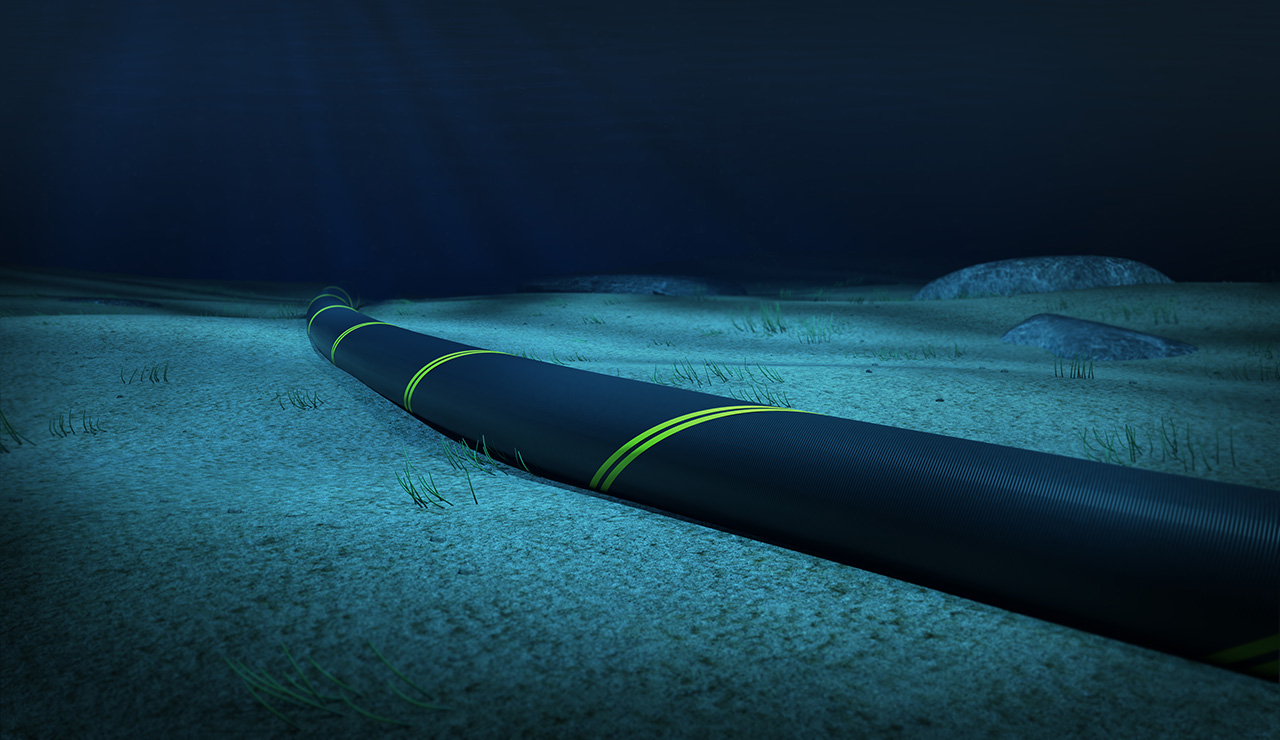
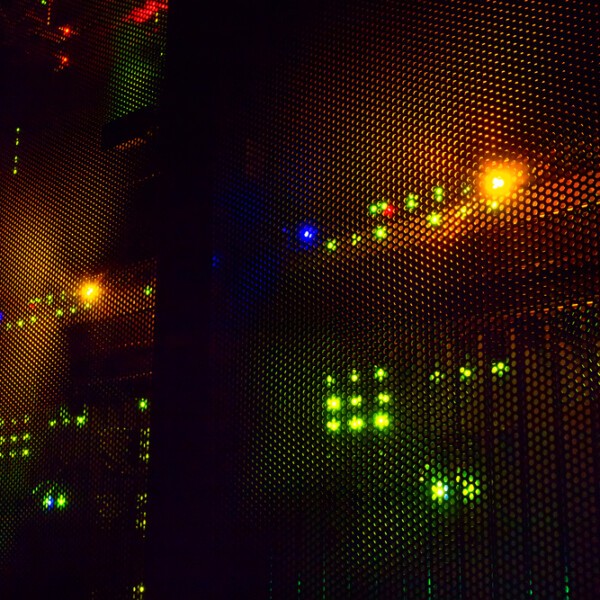






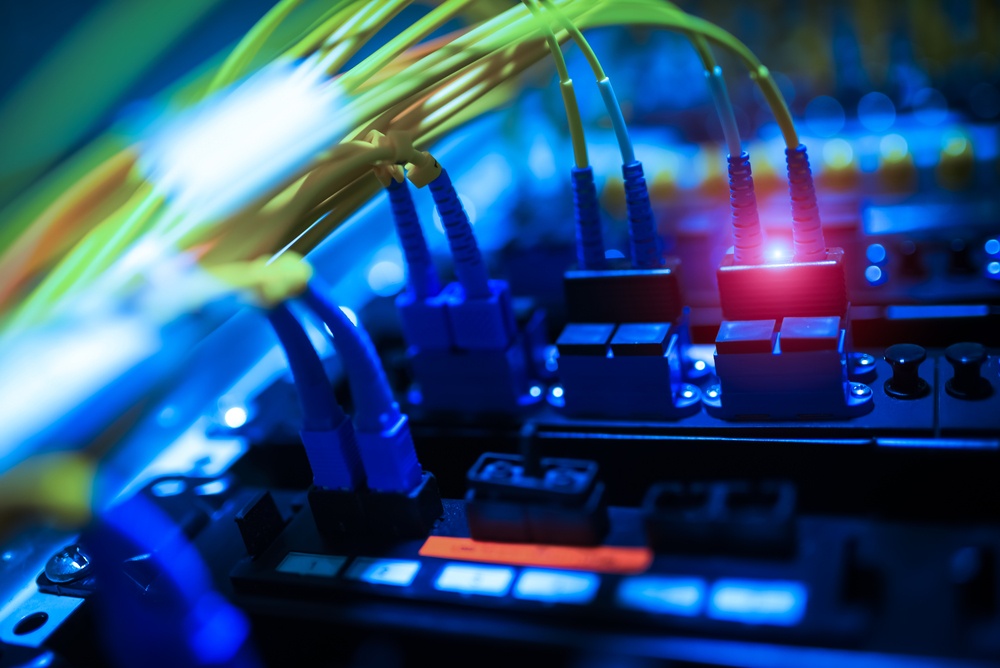












この記事へのコメントはありません。