
日本のデータセンターの電力消費量は2034年までに3倍に増加
ピーク時の電力需要の4%を占める見通し
Wood Mackenzieの報告によると、日本のデータセンターによる電力消費は2034年までに3倍に増加し、国内の電力需要増加の最大の要因になると予測されています。
この報告では、2024年の消費量19TWhが、2034年には57〜66TWhに達すると予測されており、これは約1,500万〜1,800万世帯分の年間電力使用量に相当します。ピーク時の電力需要は6.6〜7.7GWに達し、日本の総ピーク負荷の約4%を占める見込みで、現在の3倍にあたります。
この急増の背景には、日本政府がOracle、Google、マイクロソフトを公式クラウドプロバイダーとして選定したことがあり、これにより280億ドル規模のハイパースケール投資が見込まれています。ただし、報告書では、日本のデータセンターの負荷は米国の水準には及ばず、米国では2034年までにピーク需要の最大15%を占める可能性があると指摘されています。
一方で、インフラのボトルネックがプロジェクトの進行に影響を与える可能性もあります。ハイパースケーラーは通常5年以内の展開を目指しますが、成長を支えるために必要なガスタービン発電所の建設には最大10年かかることもあり、このギャップが一部の大規模データセンターや半導体工場のプロジェクトを2029年以降に押しやっていると報告されています。
電力需要は東京圏と関西圏に集中し、2030年にはこれらの地域でデータセンターが電力負荷の約7%を占めると予測されています。短期的な電力不足の懸念は少ないものの(予備率が15%以上あるため)、長期的には化石燃料への依存が脱炭素化の大きな課題となります。2034年時点でも石炭とガスが全体の40%以上を占め、再生可能エネルギーは2030年に17%に達する見込みです。
近年、主要なハイパースケーラーは日本国内で再生可能エネルギーの電力購入契約(PPA)を締結し始めています。2025年1月には、AmazonがEDP Renewables APACおよびX-Elioと太陽光発電のPPAを締結し、2024年5月には、GoogleがClean Energy Connectおよび自然電力と初のPPAを結びました。
しかし、報告書では、気候目標とハイパースケーラーの持続可能性への取り組みを両立するには、再生可能エネルギーの導入加速と原子力発電の再稼働が必要だと指摘しています。データセンターは今後、電力網の計画と投資の中心的存在となり、今後10年間で日本の電力セクターを再構築することになると結論づけています。
この流れは、国内で発表された大規模な投資計画によってさらに重要性を増しています。Googleは日本の持続可能なインフラに約6億9,000万ドルを投資する予定であり、Amazonは2027年までに、クラウドコンピューティングインフラの拡張に2兆2,600億円(約152億4,000万ドル)を投資する計画です。
この記事は海外Data Centre Dynamics発の記事をData Center Cafeが日本向けに抄訳したものです。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




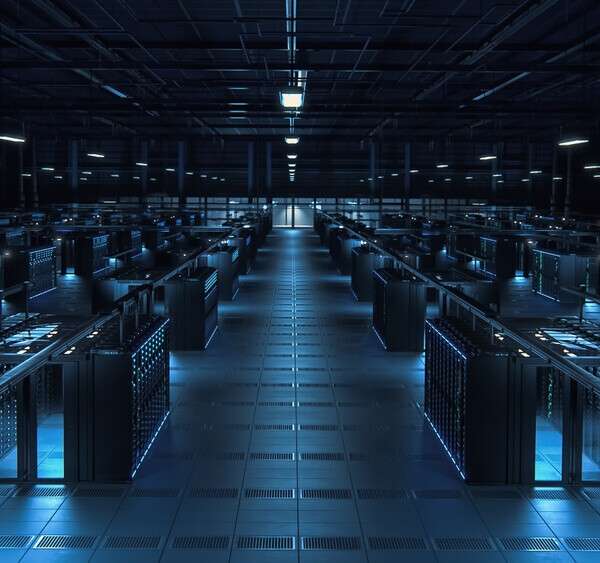

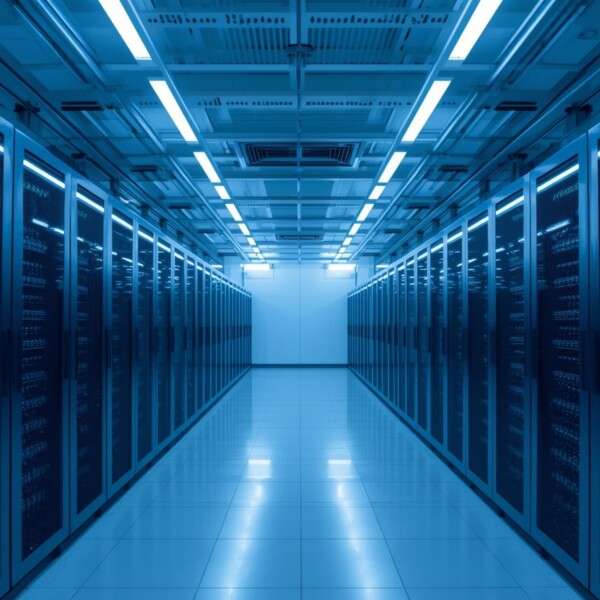



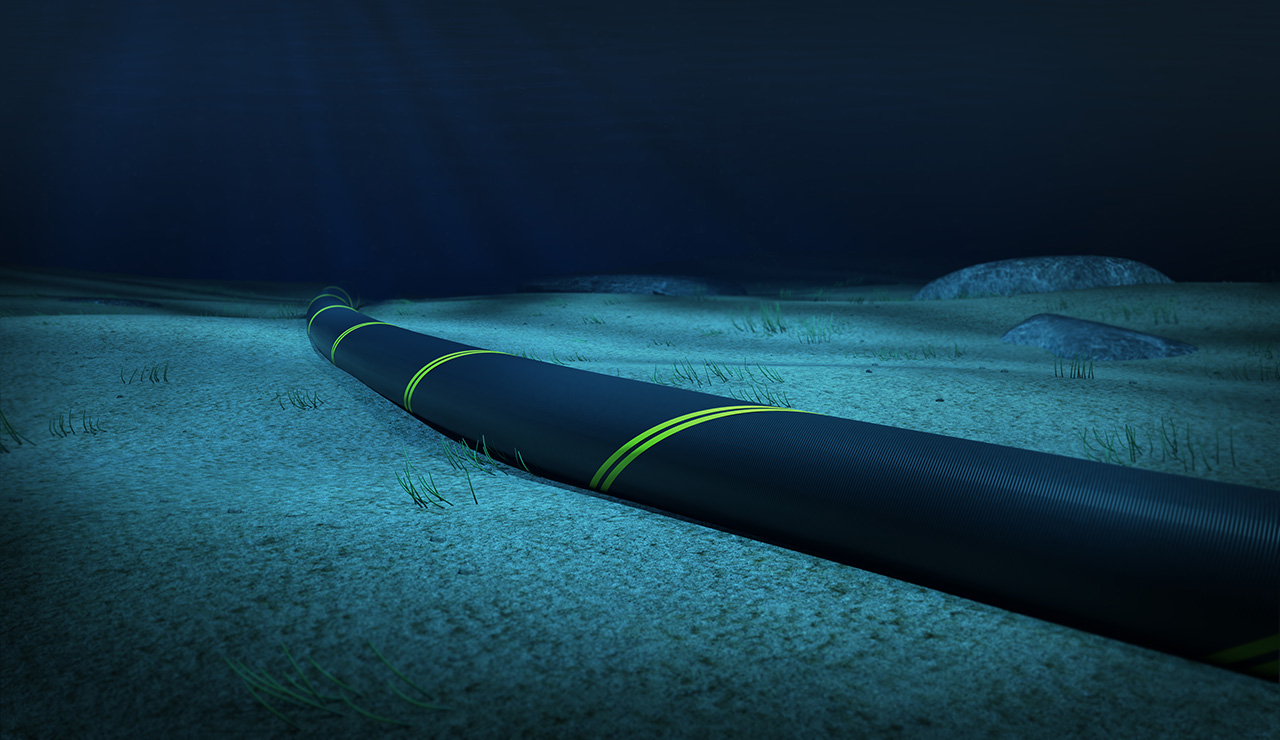
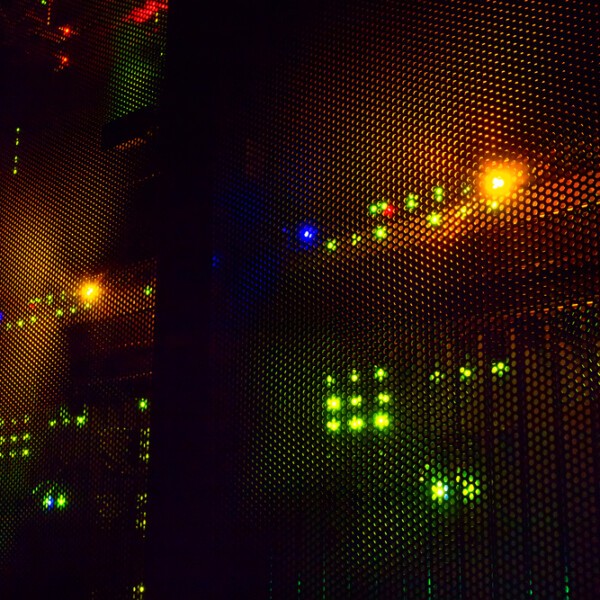




















この記事へのコメントはありません。